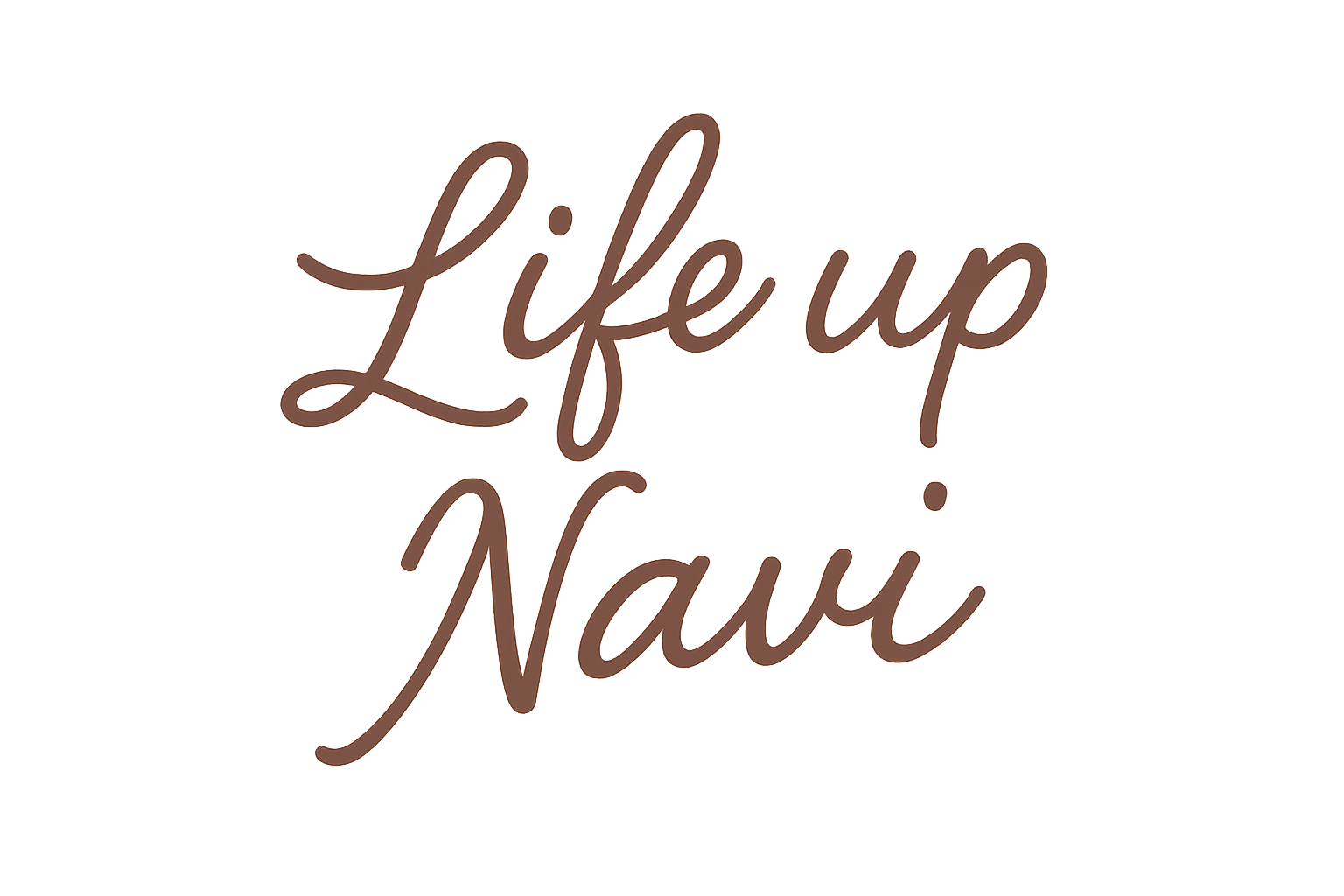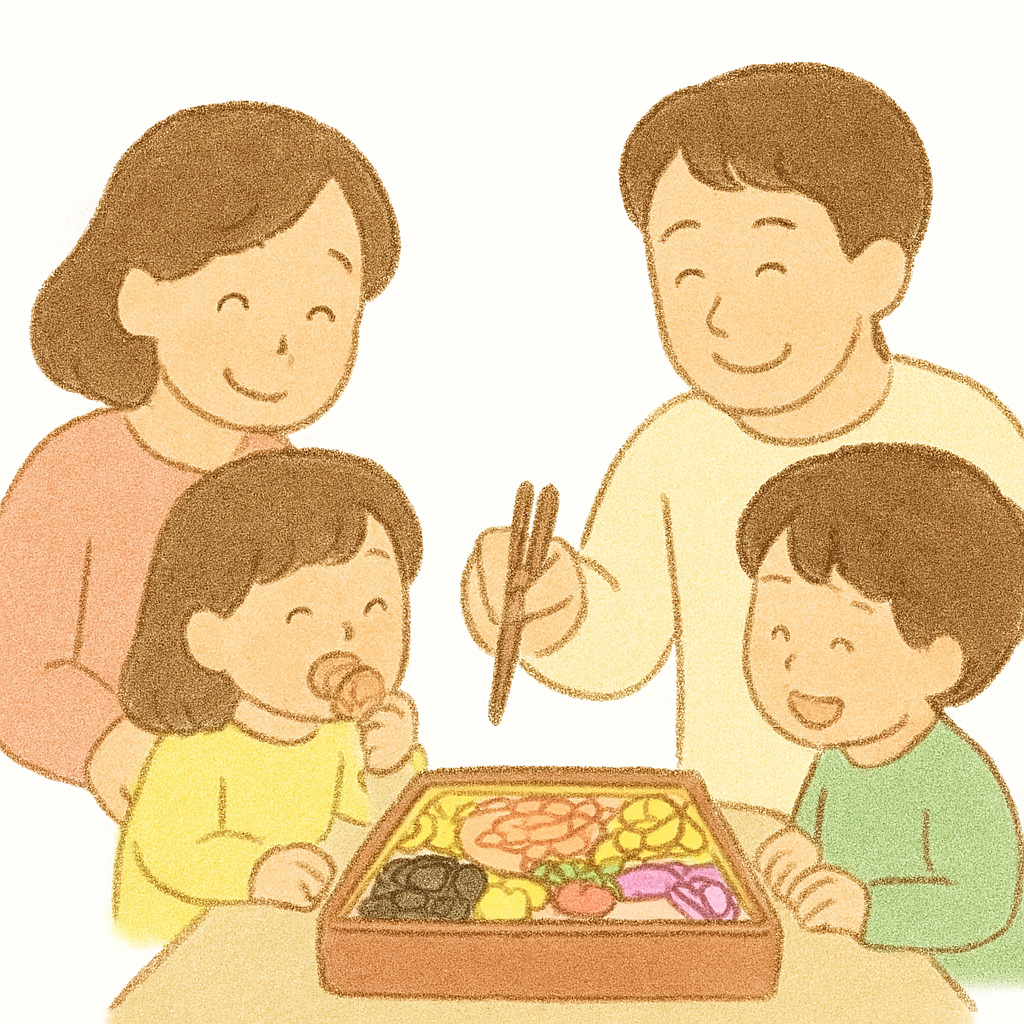新年の食卓を彩る、縁起の良い「祝い肴三種」を、手作りで迎えてみませんか?
お正月といえば、色とりどりのおせち料理が食卓に並び、新しい年の始まりを華やかに祝う日本の美しい文化ですよね。
その中でも、「祝い肴三種」と呼ばれる黒豆、数の子、田作りは、それぞれに縁起の良い意味が込められており、おせち料理には欠かせない存在です。🎍
「おせち料理は作るのが大変そう…」「手作りは難しそう…」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。でもご安心ください!この記事では、初めての方でも失敗することなく、美味しく「祝い肴三種」を手作りできるレシピと、ちょっとしたコツを丁寧にご紹介します。
手作りのおせちには、市販品にはない格別の味わいと、家族への愛情が込められます。✨
今年の新年は、ぜひご自身の手で祝い肴三種を作り、特別な気持ちで迎えてみませんか?
手作りおせちで迎える、特別な新年
【黒豆】ふっくらツヤツヤ!まめに働く願いを込めて
「まめに働く(健康で勤勉に働く)」という願いが込められた黒豆。
ふっくらとツヤのある仕上がりは、おせち料理の中でもひときわ目を引きます。ここでは、初心者の方でも失敗しない、美味しい黒豆の作り方をご紹介します。
黒豆に込められた意味
黒豆の「まめ」は、「まじめ」「健康」を意味し、一年を健康に、まじめに働くことができるようにという願いが込められています。また、黒色は邪気を払う色とされ、無病息災を願う意味もあります。
材料(作りやすい分量)
- 乾燥黒豆:200g
- 水:1.5L
- 砂糖:200g(お好みで調整)
- 醤油:大さじ1
- 塩:小さじ1/2
- 重曹:小さじ1/4(お好みで。豆を柔らかくし、シワを防ぐ効果があります)
- 錆びた釘や鉄まんじゅう(色出し用、あれば)
作り方(初心者向けステップバイステップ)
- 下準備: 黒豆は軽く洗い、鍋に入れます。水1.5Lと、あれば錆びた釘や鉄まんじゅうを入れ、一晩(8時間以上)浸水させます。この時、少量の砂糖(分量外)を加えても良いでしょう。
- 煮込み開始: 浸水させた黒豆と水をそのまま火にかけ、沸騰させます。沸騰したらアクを丁寧に取り除き、砂糖、醤油、塩、そしてお好みで重曹を加えます。
- ふっくら煮るコツ: オーブンシートなどで落とし蓋をし、ごく弱火でじっくりと煮込みます。豆が指で軽く潰れるくらい柔らかくなるまで、3〜8時間程度煮ます。途中で煮汁が減ったら、黒豆が常に浸るように差し水をしてください。
空気に触れるとシワの原因になるので、落とし蓋はしっかりとし、あまり触らないようにしましょう。 - 味をなじませる: 豆が柔らかくなったら火を止め、そのまま煮汁の中で完全に冷まします。冷める過程で味が染み込み、ふっくらと美味しく仕上がります。
失敗しないためのポイント
- **浸水はしっかりと:** 黒豆を柔らかくするためには、十分な浸水が不可欠です。冬場は特に長めに浸しましょう。
- **弱火でじっくり:** 強火で煮ると豆が踊って皮が破れたり、シワの原因になります。ごく弱火でコトコト煮るのが成功の秘訣です。
- **空気に触れさせない:** 煮ている最中に豆が空気に触れるとシワが寄りやすくなります。落とし蓋をしっかりとし、煮汁から豆が出ないように差し水をしましょう。
保存方法
清潔な保存容器に入れ、冷蔵庫で5〜6日保存可能です。
長期保存したい場合は、小分けにして冷凍保存もできます。冷凍した場合は、自然解凍で美味しくいただけます。
【数の子】子孫繁栄の願いを込めて、プチプチ食感を楽しむ
「子孫繁栄」の願いが込められた数の子。プチプチとした独特の食感と、上品な味わいが魅力です。塩抜きがポイントですが、手順を守れば初心者でも美味しく作れます。
数の子に込められた意味
数の子は、ニシンの卵であることから「二親(にしん)から多くの子が出る」という意味合いで、子孫繁栄や子宝に恵まれることを願う縁起物とされています。
材料(作りやすい分量)
- 塩数の子:200g
- **【塩抜き用】**
水:1L、塩:小さじ1 - **【漬け汁用】**
だし汁:100ml、薄口醤油:大さじ1、酒:大さじ1、みりん:大さじ1 - かつお節:適量(お好みで)
作り方(初心者向けステップバイステップ)
-
- 塩抜き: ボウルに水1Lと塩小さじ1を入れ、よく混ぜて薄い塩水を作ります。塩数の子を浸し、3〜4時間ごとに塩水を交換しながら、合計8〜12時間ほどかけて塩抜きをします。途中で端を少し食べてみて、好みの塩加減になっているか確認しましょう。
- 薄皮の除去: 塩抜きが終わったら、数の子の表面にある薄い膜(薄皮)を、水の中で優しくこすり取るようにしてきれいに剥がします。
- 漬け汁の準備: 鍋にだし汁、薄口醤油、酒、みりんを入れ、一度沸騰させてアルコールを飛ばします。火を止めてからかつお節を加え、完全に冷まします。
- 漬け込み: 薄皮を取り除いた数の子の水気を軽く拭き取り、冷めた漬け汁に浸します。冷蔵庫で一晩置くと味がよく染み込みます。
失敗しないためのポイント
- **塩抜きは焦らず丁寧に:** 塩抜きが不十分だと塩辛く、しすぎると旨味が抜けてしまいます。味見をしながら、ちょうど良い塩加減を見つけましょう。
- **薄皮は優しく:** 薄皮を剥がす際は、数の子を傷つけないように優しく扱ってください。
- **漬け汁は完全に冷ます:** 熱い漬け汁に浸すと数の子が縮んでしまうので、必ず冷ましてから漬け込みましょう。
保存方法
清潔な保存容器に入れ、冷蔵庫で3日程度保存可能です。
冷凍する場合は、漬け汁ごと保存袋に入れて冷凍し、2〜3週間を目安に食べきりましょう。
【田作り】豊作を願う、香ばしい甘辛さがやみつきに
「五穀豊穣」を願う田作りは、カリッとした食感と甘辛い味が特徴。
おやつやおつまみにもぴったりで、一度作るとやみつきになる美味しさです。初心者でも簡単に作れるレシピをご紹介します。
田作りに込められた意味
田作りは、昔、イワシを田畑の肥料として使っていたことから、豊作を願う縁起物とされています。小さな魚がたくさん獲れるように、そして豊作になるようにという願いが込められています。
材料(作りやすい分量)
- ごまめ(乾燥カタクチイワシ):40g
- いりごま:大さじ1
- **【調味料】**
醤油:大さじ1、砂糖:大さじ2、料理酒:大さじ1、みりん:大さじ1
作り方(初心者向けステップバイステップ)
- ごまめを乾煎り: フライパンにごまめを入れ、中火でじっくりと乾煎りします。焦げ付かないようにフライパンを揺らしながら、ごまめがパリッとして香ばしい香りがするまで炒りましょう。目安は8〜10分程度です。一つ食べてみて、ポキンと折れるくらいが目安。炒り終わったらバットなどに移して粗熱を取っておきます。
- タレを作る: フライパンを軽く拭き、醤油、砂糖、料理酒、みりんの調味料を全て入れます。中火にかけ、砂糖が溶けて沸騰したら弱火にし、とろみがつくまで煮詰めます。泡が大きくなり、少しねっとりとした状態になったら火を止めます。煮詰めすぎると固くなりすぎるので注意してください。
- 絡める: 火を止めた調味料のフライパンに、粗熱を取ったごまめといりごまを一度に加えます。調味料が熱いうちに、全体に均一に絡むように手早く混ぜ合わせます。
- 冷ます: クッキングシートを敷いたバットや平皿に、調味料を絡めたごまめを重ならないように薄く広げます。そのまま常温で冷ませば、カリカリとした美味しい田作りの完成です。冷めることで調味料が固まり、ごまめ同士がくっつきにくくなります。
失敗しないためのポイント
- **ごまめの乾煎り:** カリカリ食感の決め手は、乾煎りでしっかりと水分を飛ばすことです。焦がさないように注意しながら、じっくりと炒りましょう。
- **調味料の煮詰め具合:** 調味料は煮詰めすぎると固くなり、ごまめがくっつきやすくなります。とろみがつき始めたら火を止めるのがコツです。
- **手早く広げる:** 調味料を絡めたら、冷める前に素早くクッキングシートに広げることが、くっつきを防ぐポイントです。
保存方法
密封容器に入れ、冷蔵庫で約2週間保存可能です。
湿気に弱いので、乾燥剤を入れるとより長持ちします。
手作りおせちを成功させるための共通のコツ
祝い肴三種だけでなく、手作りおせち全体に共通する、成功のための大切なコツをご紹介します。これらのポイントを押さえれば、もっと楽しく、美味しくおせち作りができますよ!
- 焦らないこと:
おせち作りは、年末の忙しい時期に行うことが多いですが、焦りは禁物です。
時間に余裕を持って、一つ一つの工程を丁寧にこなすことが、失敗なく美味しく仕上げる秘訣です。
- 味見をすること:
レシピ通りに作ることも大切ですが、途中で必ず味見をして、ご自身の好みに合わせて調味料の量や塩加減を調整しましょう。
手作りの醍醐味は、自分好みの味にできることです。
- 清潔を保つこと:
おせち料理は日持ちさせるものが多いので、衛生管理は非常に重要です。
調理器具や保存容器は清潔なものを使用し、素手で触る際は手をよく洗いましょう。
- 無理なく楽しむこと:
全てのおせち料理を手作りする必要はありません。
市販品を上手に活用したり、家族で分担して作ったりするのも賢い選択です。何よりも、おせち作りを楽しむ気持ちを大切にしましょう。
まとめ:手作りの温かさで、新しい年を迎えよう
いかがでしたでしょうか?「祝い肴三種」は、それぞれに深い意味が込められた、お正月にふさわしい縁起の良い料理です。
手作りすることで、その意味をより深く感じることができ、新年の食卓がさらに特別なものになるでしょう。
この記事でご紹介したレシピとコツを参考に、ぜひ今年は手作りの祝い肴三種に挑戦してみてください。ご自身の愛情がこもったおせち料理は、きっと家族みんなの心に残る、温かい新年の思い出となるはずです。
美味しい手作りおせちと共に、笑顔あふれる素敵な新年をお迎えくださいね!🎍✨
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
美しいおせちとおもてなし正月料理 (主婦の友αブックス Cooking)