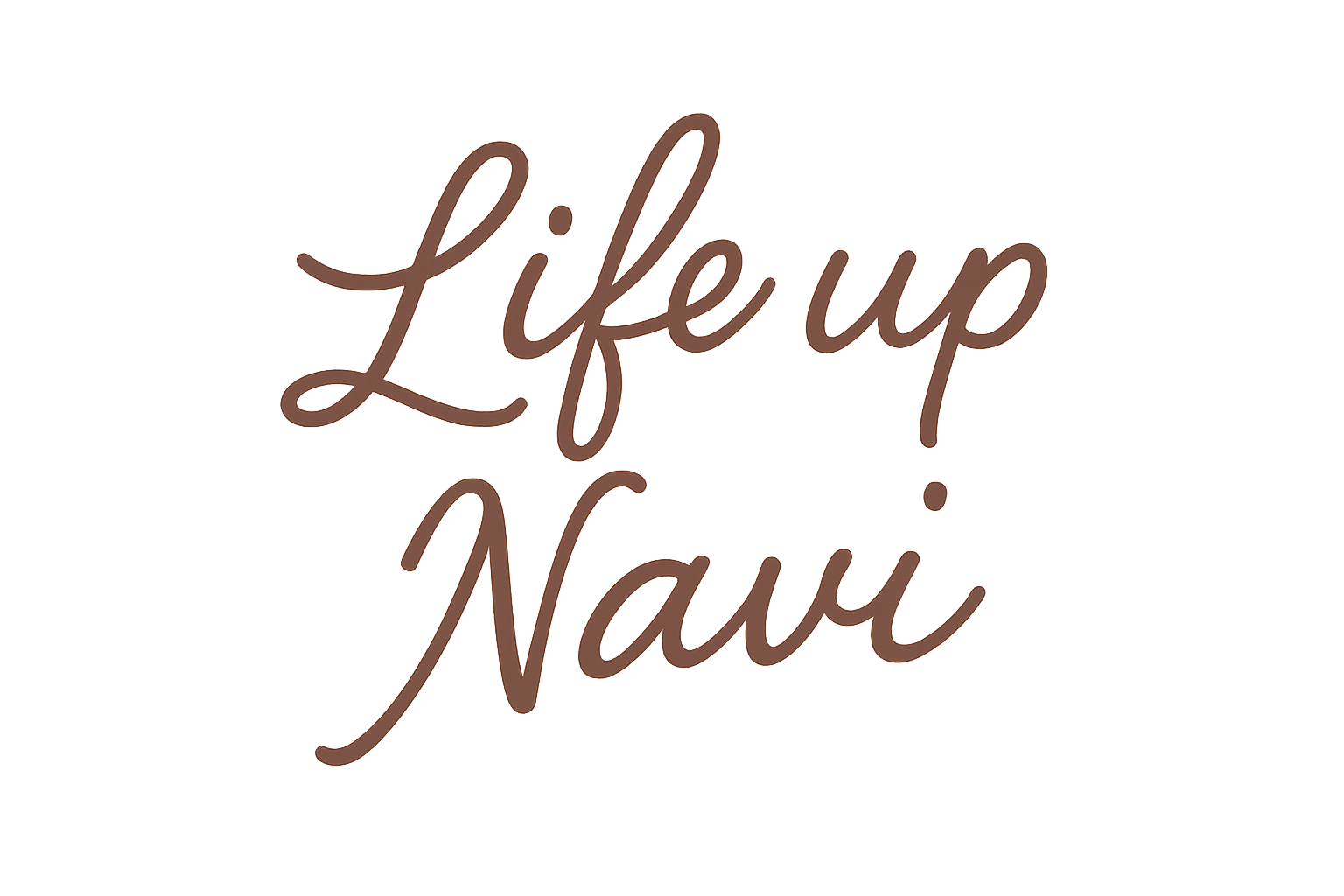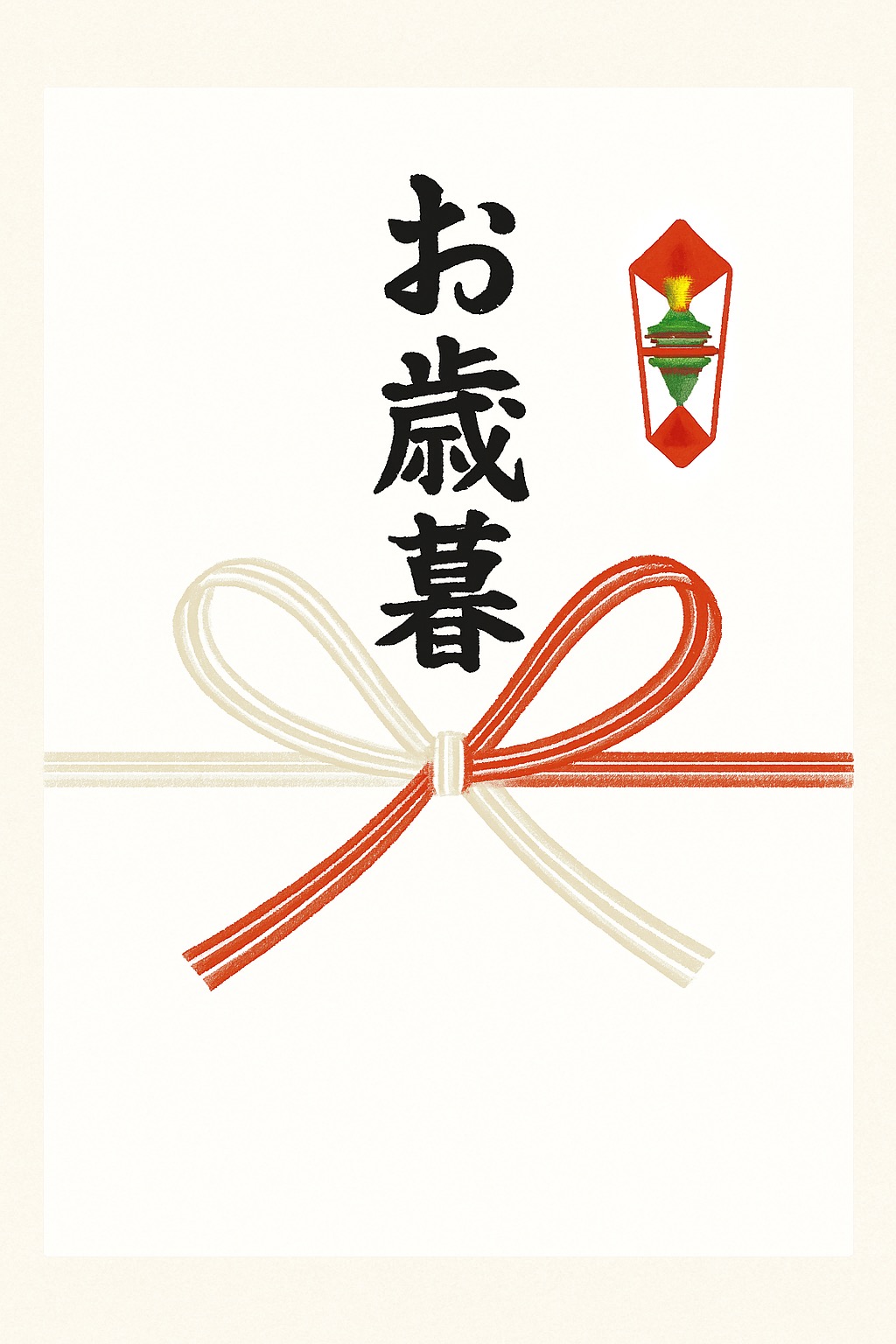一年の感謝を込めて贈るお歳暮。
品物選びと同じくらい、いや、それ以上に大切なのが、贈り物の顔となる「のし紙」の正しい書き方です。いざ書こうとすると、「名前はフルネーム?」「連名の場合はどう書くの?」「喪中の時はどうすれば…?」と、次々に疑問が湧いてきませんか?
マナー違反は、せっかくの感謝の気持ちが台無しになってしまう原因にもなりかねません。この記事では、そんなお歳暮の「のし」に関するあらゆる疑問を解決します!
相手や状況別の名前の書き方から、意外と知らない「内のし・外のし」の使い分け、そして時期を逃した場合や喪中の際の対応まで、これさえ読めば誰にでも自信を持って贈れるよう、分かりやすく解説します。
贈り物選びがまだの方はこちら
お歳暮の品物選びに迷っている方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。
>>
まずはおさらい!お歳暮の「のし紙」基本の3要素
お歳暮で使うのし紙には、3つの基本パーツがあります。
それぞれの意味を理解しておきましょう。
- 1. 水引(みずひき)
- お歳暮では、「紅白の蝶結び(花結び)」の水引を選びます。蝶結びは、何度でも結び直せることから、「何度あっても嬉しいお祝い事」に使われます。一年の感謝を表すお歳暮もこれに該当します。
- 2. 表書き(おもてがき)
- 水引の上段中央に書く、贈り物の目的です。お歳暮の場合は、シンプルに「御歳暮」または「お歳暮」と書くのが一般的です。毛筆や筆ペンを使い、楷書で丁寧に書きましょう。
- 3. 名入れ
- 水引の下段中央に、表書きより少し小さめに書く、贈り主の名前です。ここが一番悩むポイントなので、次の章で詳しく解説します。
【相手・状況別】名前の書き方マスター講座
誰が贈るかによって、名前の書き方は変わってきます。様々なパターンを見ていきましょう。
基本:個人で贈る場合
苗字だけでなく、フルネームで書くのが最も丁寧で正式なマナーです。
例:鈴木 一郎
夫婦連名で贈る場合
中央に夫のフルネームを書き、その左側に妻の名前(苗字は不要)を書きます。
例:[中央] 鈴木 一郎 [左側] 花子
家族や同僚と3名までの連名で贈る場合
一番右側に目上(年長者)の人のフルネームを書き、そこから左へ順に名前を書いていきます。役職や年齢が関係ない間柄なら、五十音順でOKです。
例:[右] 鈴木 一郎 [中央] 佐藤 次郎 [左] 高橋 三郎
4名以上の連名で贈る場合
全員の名前を書くと、ごちゃごちゃして見栄えが悪くなります。この場合は、代表者のフルネームを中央に書き、その左側に少し小さく「他一同」と書きます。そして、全員の名前を書いた紙を品物の中に同封するのがスマートです。
例:[中央] 鈴木 一郎 [左側] 他一同
職場の部署などで贈る場合は、「〇〇部一同」とします。
会社名・役職名を入れる場合
会社として贈る場合は、名前の中央右側に会社名を少し小さめに書きます。
例:[中央右] 株式会社〇〇 [中央] 代表取締役 鈴木 一郎
※個人名を出さず、会社名だけで贈る場合は、会社名を中央に書きます。
意外と知らない?「内のし」と「外のし」の使い分け
のし紙の掛け方には2種類あります。どちらを選ぶかは、贈り方によって決めるのが一般的です。
- 内のし:品物に直接のしを掛け、その上から包装紙で包む
- 【どんな時に使う?】主に配送で贈る場合に用います。包装紙の内側にあるため、配送中にのし紙が汚れたり破れたりするのを防げます。また、気持ちを控えめに表現したい時にも使われます。
- 外のし:品物を包装紙で包み、その上からのしを掛ける
- 【どんな時に使う?】主に相手の自宅へ訪問し、直接手渡しする場合に用います。贈り物の目的(「御歳暮」)や贈り主が誰なのかが、相手に一目で伝わります。
どちらが正解というわけではありませんが、この使い分けを覚えておくと、よりスマートな贈り物になります。
【困った時の対応法】時期を逃した場合・喪中の場合
特別な事情がある場合の対応方法も、大人のマナーとして知っておきましょう。
時期を逃してしまったら?
うっかり12月20日を過ぎてしまった…そんな時は、表書きを変えて対応します。
- 年内に届く場合:「御歳暮」のままでも問題ないとされていますが、気になる場合は「御挨拶」としても良いでしょう。
- 元旦〜松の内(1月7日頃)に届く場合:表書きを「御年賀」に変えます。
- 松の内以降〜立春(2月4日頃)に届く場合:表書きを「寒中御見舞」に変えます。
相手、または自分が喪中の場合は?
最も配慮が必要なケースです。お歳暮はお祝い事ではないため、基本的には贈っても問題ないとされていますが、相手の気持ちを第一に考えましょう。
【贈る側の対応】
- 贈る時期を少しずらし、「紅白の水引がない無地の短冊」を使うのが最も丁寧です。
- 表書きは「御歳暮」ではなく、「年末のご挨拶」「御挨拶」などとします。
- 四十九日が過ぎていないなど、相手がまだ落ち着かない時期であれば、贈るのを控えるのが思いやりです。その場合は、時期を改めて「寒中御見舞」として贈ると良いでしょう。
自分が喪中の場合も、相手に気を遣わせないよう、同様の対応をするのが一般的です。
まとめ:正しい「のし」で、感謝の気持ちを美しく伝えよう
のし紙は、単なる形式ではありません。あなたの大切な感謝の気持ちを、相手に敬意をもって伝えるための、日本の美しい文化です。
最初は難しく感じるかもしれませんが、一度基本を覚えてしまえば、もう迷うことはありません。この記事を参考に、自信を持って、心のこもったお歳暮を贈ってくださいね。